今回の記事では、前屈動作における腰部痛や臀部痛、下肢後面への放散痛・神経症状の評価手順や解釈の方法についてまとめていきます。

前屈動作での症状再現は、「屈曲パターン型腰痛」と考えられます。
主に屈曲動作で症状を感じるため、中腰姿勢や起立・着座動作、長時間座位保持などで症状再現されます。

臨床現場で対応することが比較的多いため、どのように評価を進めていき、どのように解釈してアプローチしていくかが非常に大切な部分になります。
評価項目毎に頭の中を整理しながら、適切な介入に繋げていけるようになりましょう!
スポンサードサーチ
前屈動作の評価方法
「あなたは、前屈動作をさせて何を見ていますか?」

前屈動作の何に注目するのが良いのでしょうか。
ただ単に前屈させて症状の有無を確認するだけでしょうか。
床面までの距離を測定することも大切です。これは動作の『量』を評価しています。
今回の記事でお伝えしたいのは、動作の『質』の部分です。
前屈する際に、どの部位を屈曲させているのか、あるいはどの部位が屈曲していかないのか、それらを評価することが大切です。
慣れもありますが、それを診ようとすること、診る力を養うことが重要になります。
前屈評価では、以下のポイントを参照すると良いでしょう。
・脊柱が滑らかに屈曲しているか
・仙骨が前傾しているか
・股関節と脊柱の屈曲の配分
・股関節と脊柱の屈曲のタイミング
・重心の前後位置
・骨盤の側方移動
・脊柱の側屈代償
矢状面上の評価ポイント
矢状面での5つのポイントを解説してきます。
・仙骨が前傾しているか
・股関節と脊柱の屈曲の配分
・股関節と脊柱の屈曲のタイミング
・重心の前後位置
脊柱の滑らかな屈曲
脊柱が滑らかに屈曲しているかは、脊柱棘突起を触診して評価します。
突出して凸になっている部分がないか、あるいは凹んでいる部分がないかを確認しましょう。
凸の部分は過屈曲、凹んでいる部分は平坦・伸展しているという解釈になります。
おそらくですが、過屈曲している部分がある場合、どこかの部位が平坦・伸展している可能性があります。凸の部分よりは、平坦・伸展している部分に対してアプローチをすることが多くなるでしょう。
仙骨の前傾
その流れで、仙骨が前傾しているのかを評価しましょう。
適切に仙骨が前傾していなければL5とS1の間でヒンジしてしまい、周囲組織への負担、特に椎間板への負荷が増します。
股関節屈曲と脊柱屈曲の配分
仙骨が前傾しているということは、骨盤が前傾しているとも捉えられます。
つまり、股関節屈曲動作に影響してきます。
前屈動作を評価する時に、主に脊柱屈曲で行っているのか、あるいは股関節屈曲で行っているかを見極めることが大切です。
屈曲パターン型腰痛の場合、脊柱屈曲メインでの前屈動作を行う傾向があります。
トータルの屈曲量を脊柱で補うのか、股関節で補うのか配分を考慮することで、アプローチ部位が変わってきます。
股関節屈曲と脊柱屈曲のタイミング
股関節屈曲と脊柱屈曲の動作が行われるタイミングを評価してきます。
最初から最後まで脊柱でしか屈曲しないのか、最初は脊柱で徐々に股関節が屈曲してくるのか、最初は股関節で後から脊柱が屈曲してくるのか、動作パターンは様々です。
パターン化された動作を、違うパターンへと誘導するためには、とても重要な評価になります。
重心位置
最後に重心位置についてですが、これは前屈動作の際に下半身重心に対して上半身重心がどのような位置関係になっているかです。
股関節屈曲が少なく脊柱屈曲がメインの場合は、下半身重心が直立姿勢の時と変わらず、上半身重心だけが前方へ移動していきます。この場合は前方重心となっています。
反対に、脊柱屈曲が少なく股関節屈曲がメインの場合は、臀部が後方へ移動して下半身重心が後方へ移動し、上半身重心の前方移動が少なくなります。この場合は後方重心が強くなっています。
特に問題となるのは前方重心の場合で、下位腰部に対するメカニカルストレスが増大します。後方重心の場合は脊柱の滑らかな屈曲ができないため、屈曲パターンよりも伸展パターン型腰痛を引き起こしやすいと考えられます。
スポンサードサーチ
前額面上の評価ポイント
前額面では、以下の2つのポイントを解説してきます。
・脊柱の側屈代償
前屈は矢状面上の動作であるため、基本的には矢状面上のトラブルを考慮することが重要となります。
しかし、片側における矢状面上の機能不全がある場合、前額面上での代償を引き起こす可能性があります。
骨盤の側方移動
片側の股関節屈曲機能不全がある場合、前屈動作では骨盤の側方移動が生じる可能性があります。
場合によっては、骨盤回旋での代償、側方移動と回旋を併せて代償することもあります。
例えば、前屈動作で骨盤が右側へ側方移動した場合、右側の股関節屈曲が強まり、反対に左側の股関節屈曲は弱まります。
左側の股関節屈曲の可動域制限がある場合、左側での股関節屈曲動作を避けるようにして前屈することになるでしょう。
もちろん、前屈動作だけで片側股関節の機能不全と断定せず、後述する他の評価と組み合わせて考慮する必要があります。
脊柱の側屈
片側の脊柱起立筋が短縮・緊張している場合や、片側椎間関節の可動性制限がある場合、脊柱の側屈代償が生じる可能性があります。
例えば、前屈動作で脊柱が右側屈した場合、右側の脊柱起立筋の短縮を示唆します。筋緊張に関しては、左側は伸張位での緊張、右側は短縮位での緊張と捉えることができます。
背側面から見た場合、脊柱起立筋の膨隆に左右差が生じているかもしれませんので、視診・触診と組み合わせて行うことを推奨します。
脊柱が右側屈した場合では、右側椎間関節の可動性制限が考えられます。前屈動作において椎間関節では、下位椎体に対して上位椎体が上方・腹側方向へと滑る動きが生じなくてはなりません。右椎間関節の制限がある場合、上位椎体の上方滑りの動きが生じないため、左椎間関節だけは動くために脊柱が側屈していきます。
前屈動作を分解する
上記では、前屈動作の質を評価するポイントをまとめましたが、その先に“何を”・“どのように”評価していくべきなのかを頭に入れておく必要があります。
ここまでの内容でお気付きかと思いますが、前屈動作は主に脊柱屈曲と股関節屈曲の2つに分解することができます。
それぞれどのように評価していくべきかを解説していきます。
スポンサードサーチ
脊柱屈曲
脊柱屈曲の評価では、以下の2つの肢位を考慮します。
②正座での脊柱屈曲
どちらの評価も、脊柱が滑らかなに屈曲しているかがポイントになります。
①座位脊柱屈曲
座位での脊柱屈曲動作は、骨盤帯より遠位の要素が除外される上、骨盤帯が安定した上での脊柱屈曲の可動性を評価することができます。
股関節屈曲位のため、下肢後面筋群の伸張制限も除外しています。
②正座脊柱屈曲
正座での脊柱屈曲動作は、座位とは違い抗重力位ではありません。
座位と同様に骨盤帯は安定しておりますが、脊柱に対する重力負荷が変わるため、動作に伴う筋活動に違いがあります。正座で行うことで、脊柱屈曲の純粋な可動性を有するのかを評価することが可能です。
余談ですが、正座脊柱屈曲位のことをLocking Position / Lumbar Locked Positionと言ったりもします。共通言語として覚えておくと便利です。
股関節屈曲
股関節屈曲の評価では、以下の2つの評価を考慮します。
②背臥位股関節屈曲
①SLR
SLRの角度は、Activeであれば70度、Passiveであれば80度は確保したいところです。
前屈動作では、両脚同時に下肢後面筋群が伸張されていきますが、SLRでは片側における下肢後面筋群の伸張性を評価することができます。
そのため、左右差がある場合は骨盤帯の側方移動や回旋の代償を引き起こしたり、さらにそこから代償して脊柱側屈を引き起こす可能性があります。
また、前屈は荷重下の動作ですが、SLRは非荷重下の動作です。荷重の有無によってフィードバックが変わるため筋活動の違いが生じたりもします。足部・足関節の機能不全を有する場合は、荷重下になると下肢の筋緊張が増大させて安定性を補完しているかもしれません。
以下、前屈とSLRの関係性の示唆です。
前屈制限あり、SLR制限なし:足関節・足部機能不全を示唆する
②背臥位股関節屈曲
背臥位股関節屈曲の角度は、100度程度を確保できていれば良いかと思います。
参考可動域角度は125度ですが、この角度まで行こうとすると腰部・骨盤帯の動きも加わってしまうため注意が必要と感じます。
SLRは膝関節伸展位での股関節屈曲になりますが、背臥位での股関節屈曲は膝関節屈曲位で実施します。そのため、ハムストリングや腓腹筋など下肢後面の伸張性収縮の影響を減らすことができます。
以下、SLRと背臥位股関節屈曲の関係性の示唆です。
SLR制限あり、背臥位股関節屈曲制限なし:下肢後面筋群の伸張性制限
股関節屈曲の可動性制限の場合、股関節内旋・外旋の可動性の評価、寛骨に対する大腿骨の副運動検査、臀部や鼠蹊部など股関節周囲軟部組織の評価を行う必要があります。
下肢後面筋群の伸張性制限の場合、ハムストリングの内側or外側or両側なのか、腓腹筋の内側or外側or両側なのか、ハムストリング〜腓腹筋の内側or外側なのか、様々なバリエーションを考慮していきましょう。
SLRに関しては、こちらの記事で詳しく解説しているのでご参照ください。
スポンサードサーチ
まとめ
前屈は臨床現場でも汎用性の高い評価です。
その後に続く脊柱や股関節の評価も既に行っている方は多いと思います。むしろ知らない方はごく少数ではないでしょうか。
これら評価の組み合わせによって、介入するべき部位はかなりはっきりしてきます。
臨床現場では、なるべく評価時間を短縮して介入に繋げることが第一優先です。
上記の内容を頭に入れておくことで、前屈パターンの機能不全を適切に把握して、症状があれば改善に導くスピードを速めることができるでしょう。
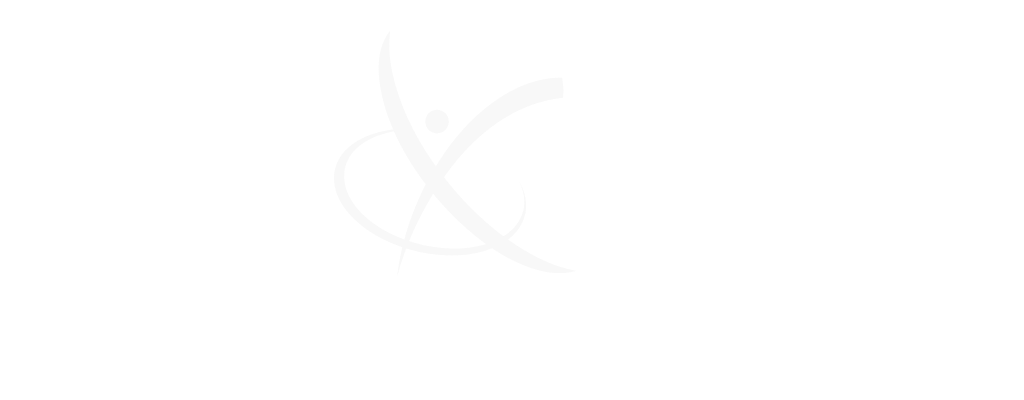




コメント