顎関節症の評価
今回の記事では、顎関節症の評価方法をご紹介していきます。
まず、顎関節症の可能性が高いのか、そうではないのかを鑑別する必要があります。
顎関節症と鑑別するべき疾患・障害は、感染症・炎症症状・代謝性疾患や自己免疫疾患になります。口が全く開かないということはありません。基準としては”2~2.5横指”開口することがポイントです。それ以外の場合は、上記の疾患の可能性があります。
その他には、顎関節部や咀嚼筋部の腫脹や安静時痛、発熱している場合や他の関節部位に症状が生じている場合も同様に、顎関節症ではない可能性があります。
これらの症状がないことを踏まえた上で、以下の評価を進めていきましょう!
以下の評価のポイントは、無料会員様のみ閲覧可能です。
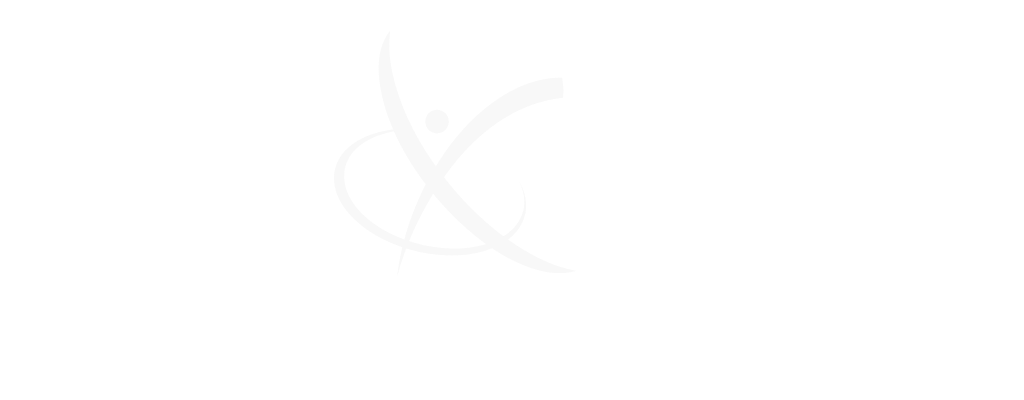
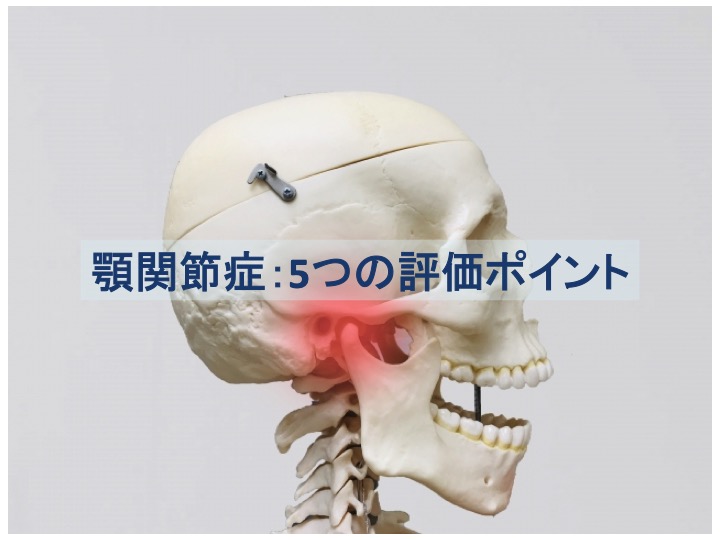


コメント